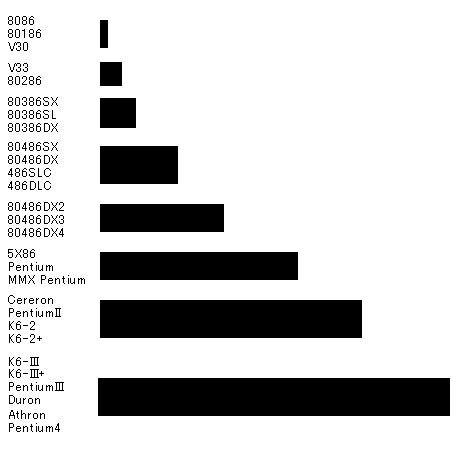メモリの増設と注意点 メモリの増設と注意点
メモリを増設することにより、全体的なパフォーマンスアップを図る事ができます。
ましてPC-98は標準16Mや30Mといった機種がほとんどなので、これはもう必須と呼べるでしょう。
そこで、Windowsにおけるメモリ増設の注意点と、ポイントを考えてみます。
 増設単位
増設単位
後発(X以降)のPC-98は主にSIMM、EDO-RAM、SD-RAM(シンクロナスD-RAM/DIMM)の3種類のメモリが使用できます。
これらの組み合わせによってパフォーマンスが上下する場合がありますので、パフォーマンスが高い順に並べてみました。
※32M単位での計測で10位まで掲載します。
| 1最も高速 |
DIMM32M=32M |
| 2 |
DIMM64M又はEDO32M=64or32M |
| 3 |
DIMM32M+DIMM32M=64M |
| 4 |
DIMM32M+EDO32M=64M |
| 5 |
EDO32M+EDO32M=64M |
| 6 |
DIMM64M+EDO32M=96M |
| 7 |
DIMM64M+DIMM64M=128M |
| 8 |
DIMM64M+EDO32MX2=128M |
| 9 |
DIMM32M+SIMM32M=64M |
| 10最も低速 |
DIMM64M+SIMM32M=96M |
|
といった結果になりました。見て分かる通りなのですが、DIMMが最も高速で、EDO、SIMMの順にアクセス速度が遅くなっているのが分かります。
またメモリを増設すればするほど、速度的なパフォーマンスは殺されてしまうことが分かると思います。
メモリばかりは増設しただけ快適になるという訳ではないようです。
DIMMで2枚挿しの128Mを実現した場合、EDOと組み合わせた場合より遅い結果になってしまったのにも原因があります。
実はWindowsはPC-98、DOS/Vに関係なく内蔵メモリを96M単位に区切って管理するという特徴があるからなのです。
同じタイプのメモリの組み合わせでも96Mと128Mでは差があります。
また192Mと256Mでも大きな差が現れます。
つまり96Mと256Mでは、その差が倍以上開く計算になります。
特に大きな画像ばかりを扱う条件が無い場合や、特別大きなメモリを必要としていないのならば、無駄な増設をしない事が、性能を最大限生かす事につながるとも言えます。
重たい処理(DVD再生等)をさせていて、処理が重たく感じた場合、メモリを増やすのではなく、逆に減らす事で解決できてしまったという例も数多くあります。
PCIレジスタの書き換えツール(Intelsat,pciwrite等)でEDOに対するアクセス速度を最適化するという手もありますが、これを利用しても快適に使用できるという範囲では
8番のDIMM64M1枚+EDO32M2枚挿し=128Mまでが限界ではないでしょうか。
なおIntel430VX系チップセットのPCIレジスタ設定は58
55のみの記述。または58 D5と56 14の複合記述が最適(安定して使用できる限界)と思われます。
もちろんマシンによって個体差もありますので、色々試してみるのも手です。
<豆知識:Intelsat,pciwrite>
PCIレジスタの内容を書き換えることのできるツール。メーカーはあらかじめマシンが安定動作する様に必要以上にマージン(ウェイト)を持たせてPCを出荷しています。
このマージンを削り、根本的な高速化を行うことができるソフトウェアの名前です。
搭載されているチップセットやマシンの個体差によって設定できる範囲が変わるので、必ず決定したデータを公開できるものではないというのが難点ですが、PC-98はDOS/Vに比べ、高いマージンを持たせている場合が多いので、これを取り払うことによって体感できるほどの高速化を行う事ができる場合があります。
またPCIを持たないPC-98の場合でもコストダウンなどの目的でPCIレジスタが存在する場合があり、これらの機種にも有効な場合があります。
WildCatやIntel430VX/HX/FX等のチップセットを搭載しているPC-98ユーザーは試してみる価値があるかもしれません。
 CPU強化
CPU強化
演算処理を高速化するにはCPU交換は必要不可欠です。
後発PC-98はソケット5/7(Pentiumソケット)を持っているので、AMD
K6シリーズが使用できます。
メルコ社のHK6-MD-NV4シリーズを使用すれば簡単にパワーアップが可能です。
これらのCPUアクセラレータ用の下駄部分を利用してK6-IIIE+550MHz等のCPUに交換し、さらに600MHzにオーバークロックという事も可能ですが、K6-IIIE+を搭載するとUSBが不安定になるなどの不具合が報告されているため、あまり推奨してはいません。
ただK6-III等のフルスピードバックサイドキャッシュは魅力です。
K6-III450で466MHzのオーバークロックは全く問題なく安定動作しますので、本来はこの範囲以下で使用するのが無難ではないかと思われます。
450のK6-IIIを500MHzまでクロックアップさせるとさすがに不安定になる場合があります。
PC-98でのDVD再生にK6-IIIは必須に近い条件なので見かけたら迷わず買いましょう。
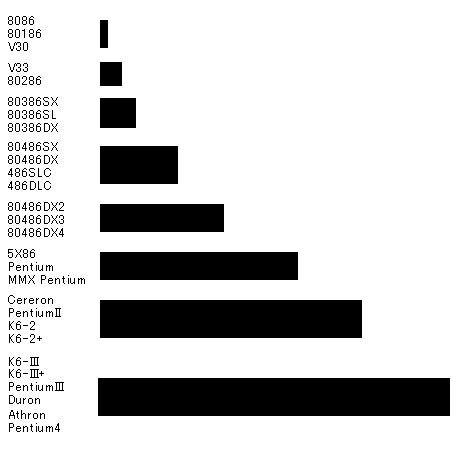 |
V30クラス
今はコレクション的な価値に留まっています。
286クラス
初期のDOSゲームをするには最適。
386クラス
中期以降のDOSゲームをするには最適。
486DXクラス
Windows3.1ベースで使用するには最低このクラス以上が必要。
486DX2クラス
Windows3.x環境を快適に使用するには最低このクラス以上が必要。
Pentiumクラス
Windows95を使用するには最低このクラス以上が必要。
PentiumIIクラス
95OSR2、98環境等で快適に使用するには最低このクラス以上が必要。
PentiumIIIクラス
現在の所、このレベルであれば、処理速度的に問題となる事は無いでしょう。 |
600MHz化の例 (NV4下駄+K6-IIIE+550 または N4下駄+K6-IIIE+550)
ベースクロック66MHzに設定 クロックマルチプライヤ1.5倍設定
CPUクロック6倍設定 = 600MHz
かなり無茶ですがN4下駄を使用して450MHzのK6-IIIがオーバークロック600MHzで動作したという報告も上がっています。
実際にこれと同じ事をするアクセラレータも発売されています。
メルコ製ですが、カタログにも載らずWEB上の製品リストにも公開されていないため、知名度は非常に低い製品です。
HK6-MS600P-NV4という製品名です。
詳しい情報はオーバーチューンのCPUコーナーに書かれています。
 速度の測定/RTB
速度の測定/RTB
CPUの性能はマザーボードに依存するテクノロジやチップセットの性能に同じく、パソコンの全体的なパフォーマンスに大きく影響します。
CPU交換前のパフォーマンスと比較して、どの程度の違いがあるのか、客観的に見るにはベンチマークソフトと呼ばれる主に処理速度等を計測する専用のソフトウェアを使用すると簡単です。
しかしながら一般的なベンチマークプログラムの多くは、その計測ルーチン(実際に処理速度を計測するプログラム部分)がCPUキャッシュ内に全て収まるよう設計されており、サイズも大きく繰り返し処理の少ないWindowsアプリケーションを実行した場合の実際の処理速度と比較した場合に、思いがけないほど高い数値が表示されてしまう事があります。
CPUキャッシュやMMXといったサブテクノロジは、あくまでCPUを支援する補助的な機能の為、これを最大限に有効に利用できる場合と、そうでない場合とでは体感速度に相当量の違いが現れてしまいます。
ベンチマークでは倍近くの値が表示されているのに、実際に使用してみると、倍ほど速くなったようには感じられないという事はよくあることですが、こういったサブテクノロジを極力排除しマザーボードに依存するテクノロジやCPUの純粋な処理速度を計測することで、体感速度に近い結果を見る事ができるようになります。
|